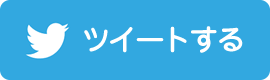自然・風景
【連載】つめの里山雑記⑦
「コハクチョウが連れてくる季節」
おかえり!コハクチョウ。
今年は、9月に入っても暑い日が続いた。例年であれば、もう1か月もしないうちにコハクチョウが初飛来するはずだが、そんな気配を感じさせない。
しかし、10月に入り朝夕が冷え込むようになった。すると、10月7日早朝、大山下池に8羽のコハクチョウが初飛来した。庄内の人が季節の移り変わりを感じる瞬間だ。

初飛来から高館山の紅葉が美しい11月上旬までの期間は、たくさんの人がコハクチョウを見に大山上池・下池を訪れる。

今年は、幸いにも地元の小学生たちもその姿を見ることが出来た。いつもの年であれば、総合学習は9月で現地学習を終えるのだが、今年はコロナ禍の影響もあり、10月も授業が実施された。羽音を立てながら、自分たちの頭上を越えて、田んぼに飛んでいくコハクチョウたちの姿は子どもたちの目にしっかり焼きついたと思う。

コハクチョウはどうして庄内にやってくる。
庄内では、コハクチョウは10月から3月頃まで見られる渡り鳥(冬鳥)だ。春から夏の間は、ロシア極東部等の湿地で繁殖、子育てをしながら暮らしている。9月になると、これから来る厳しい冬を避け、日本(庄内地域にも)にやってくる。
ある調査では、コハクチョウは約4000~5000kmの距離を休憩しながら、およそ40日間かけて日本にやってくるという。本当に長い旅をして、庄内にやってきてくれるのだ。

また、今でこそハクチョウが田んぼにいるのは当たり前の光景だが、昔からいたわけではない。昔は、冬になると採餌場である田んぼは雪で覆われ、池も結氷するため越冬するには厳しい環境だった。池などで越冬するようになったのは温暖化が進み、池が凍らなくなった1980年代後半だといわれている。


庄内平野とコハクチョウ
コハクチョウにとって、庄内地域は越冬するのに最適な場所だ。なぜなら、この地域には庄内平野が広がり、田んぼには収穫の際に落ちた米(落穂)がたくさんあるからだ。朝、川や池から飛び立ち、その落穂を食べる。中には泥の中に顔を入れて餌を食べている姿もみることができる。



夕暮れ、池の主役が交代する
日が暮れ始めると、池に続々とコハクチョウが戻ってくる。そして、あたりが暗くなり、月や星が輝きだすと池から一斉にマガモたちが飛び立つ。
一瞬で池の上空は、コハクチョウとカモでいっぱいになる。お互いにぶつからないように交差して飛んでいるその姿は、言葉に言い表せない生きものの力強さを感じる。

私が働く自然学習交流館ほとりあでは玄関から入ってすぐの場所に野鳥情報コーナーを設置している。その時、施設周辺で確認できる野鳥の種類や数を公開しているので、ぜひ野鳥観察する際の参考にしてほしい。

まだまだ、お伝えしたい渡り鳥のことがたくさんあった。
その話は、また次回にお伝えしたいと思う。
環境教育工房LinX Facebook
鶴岡市自然学習交流館ほとりあ HP
鶴岡市自然学習交流館ほとりあ Facebook
鶴岡市自然学習交流館ほとりあ Instagram
鶴岡市自然学習交流館ほとりあ twitter
上山剛司Ueyama Takeshi
北海道、長崎対馬と渡り歩き、今では庄内弁も理解できるようになった薩摩隼人。目下の楽しみは、息子とかあちゃんとの週末の里山散策。仕事でもプライベートでも「人」と「自然」の新しいかかわり方について模索中。環境教育工房LinX主宰、自然学習交流館ほとりあ学芸員兼副館長。